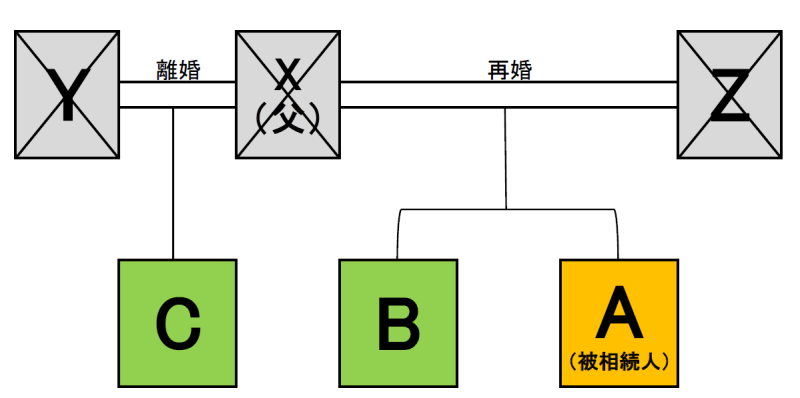遺言で、5年以内の期間であれば、遺産の分割を禁じることができます。
そもそも、遺産分割は、相続が発生した後であれば、いつでも行なってよいとされていて、時期的制限は設けられていません。
たとえば、相続人のうち一人が若年者である場合、「 判断能力が未成熟であるため、判断能力が成熟するまで遺産の分割を禁じる 」、といった遺言を生前に残すことによって、遺産分割の早期分割を防ぐことができます。
このような場合で遺言がなければ、相続が発生してすぐに遺産が分割されてしまい、相続紛争が深刻化するといった事態も予想されるので、一定期間は遺産の分割を禁止する、実益があると言えます。
上記民法第908条で定められているとおり、被相続人は、生前に遺言をのこすことによって、5年以内の期間内であれば、遺産の全部またはその一部について、分割を禁ずることができるのです。
ちなみにこの遺産分割の禁止は、生前であれば、かならず遺言によって行なう必要があります(生前に行なう場合、遺言以外の方法で指定することは認められません)。
また、生前ではなく、相続が開始された後であれば、家庭裁判所によっても遺産分割を禁ずることができます。
相続が開始された後に、「 特別の事由 」 がある場合、家庭裁判所は、遺産の全部またはその一部について、期間を定めて遺産の分割を禁じることができます。
上記でいう 「 特別の事由 」 とは、すぐに遺産分割を行なうべきではない、ふさわしくない理由のことを指しています。
たとえば、冒頭例としてあげた、「相続人が若年者」である場合がこれに当たります。
その他、相続人全員が合意するならば、一定期間遺産の分割を禁じることもできます。
そもそも、相続人全員が納得して遺産を分配し合うのが、本来の形であるため、相続人全員が納得さえしていれば、遺産を共有化しておいても問題ない、というのは当然の話ですね
以上、遺産分割の禁止についてのお話しでした

相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから